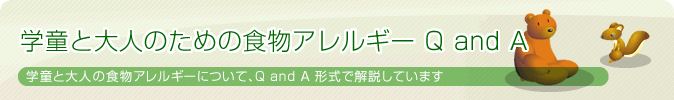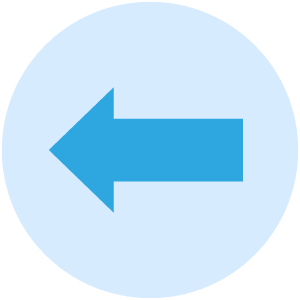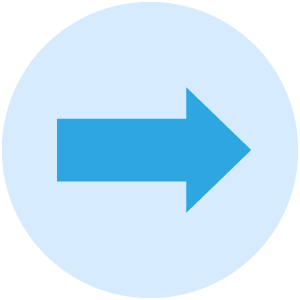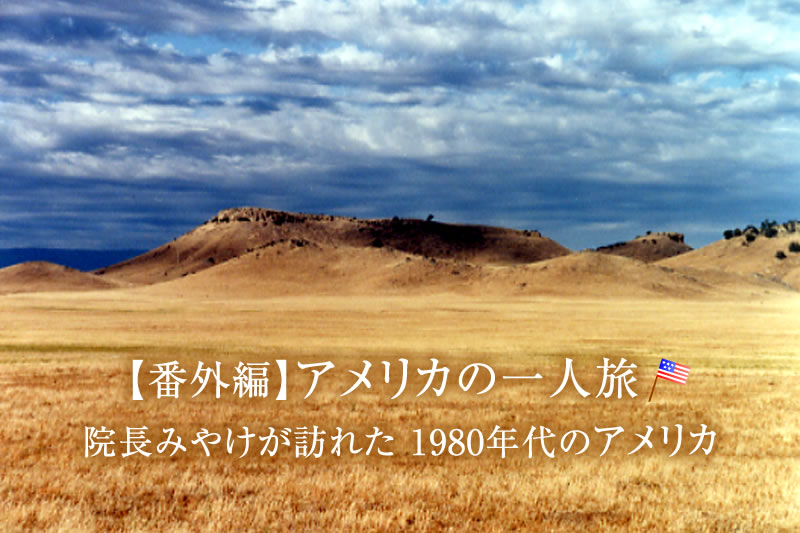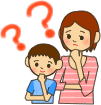 Q7:食物依存性運動誘発性アナフィラキシーはどうして起こるのですか?
Q7:食物依存性運動誘発性アナフィラキシーはどうして起こるのですか?
 A7:食物依存性運動誘発性アナフィラキシー(FDEIA)は特定の食物を食べた後に運動をすることによって誘発されるアナフィラキシーであり、じんま疹、まぶたや口唇のはれ、喘鳴、悪心おう吐、腹痛、頭痛、咽頭浮腫、血圧低下などの症状が起こります。
A7:食物依存性運動誘発性アナフィラキシー(FDEIA)は特定の食物を食べた後に運動をすることによって誘発されるアナフィラキシーであり、じんま疹、まぶたや口唇のはれ、喘鳴、悪心おう吐、腹痛、頭痛、咽頭浮腫、血圧低下などの症状が起こります。
FDEIAでは特定の食物に対するアレルギーがあり、その食物を食べただけではアレルギー症状は起こりませんが、摂取後に運動をすると症状が起こります。
日本におけるFDEIAの原因食物は小麦がもっとも多く、次いでエビですが、この2つの食物が原因の80%以上を占めます。以下はイカ、カニ、ブドウ、ナッツ、ソバなどで、魚や貝により発症した例もあります。
小麦によるFDEIAの原因抗原は小麦成分のグルテンに含まれるω-5グリアジンが主な原因であることが判明しました。小麦のFDEIAでは小麦やグルテンの特異的IgE抗体は陽性になりにくいですが、抗ω-5グリアジン特異的IgE抗体検査には感度がよく、小麦FDEIAの80%で陽性になると報告されています。
FDEIAは食物摂取と運動の組み合わせだけでなく、食物摂取と非ステロイド系鎮痛薬(NSAIDs:現在、鎮痛薬や解熱剤として使用される多くの薬剤)の組み合わせでも起こることがあります。あるいは食物と運動、非ステロイド系鎮痛薬の三者がそろって初めて起こる場合もあります。
しだいにFDEIAの発症機序が明らかになってきました。これによると、安静時には小麦摂取をした後に血中ω-5グリアジンが検出されなかったのに対して、小麦摂取と運動やアスピリン投与の組み合わせでは、血中ω-5グリアジンが検出されるようになりました。
すなわち、安静時には原因食物の抗原は消化管で小さなペプチドやアミノ酸に分解され、抗原性を失った後に吸収されるため、体内に入ってもアレルギー症状は起こしません。しかし、運動や非ステロイド系消炎鎮痛薬を内服した場合は、十分に消化されていない食物抗原が吸収されてしまうため、アレルギー症状を起こすことになります。
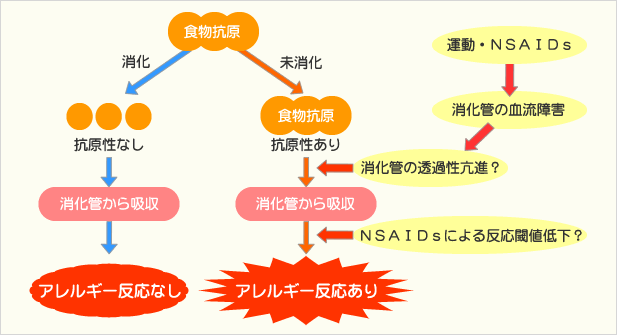
運動やアスピリンがどのようにして消化管での吸収を促進するのかはまだ不明ですが、非ステロイド系消炎鎮痛薬による消化管障害は消化管の血流と関連しており、運動による消化管障害も血流障害と関連している可能性が高いと考えられます。
消化管における何らかのアレルギー反応が、原因食物アレルゲンの吸収促進と関連していると考えられます。一方で、アスピリンなどの非ステロイド系消炎鎮痛薬は肥満細胞からのヒスタミン遊離を促進する可能性も指摘されています。
参考文献:
1)日本医事新報 No4564、2011.10.15
※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。
※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。