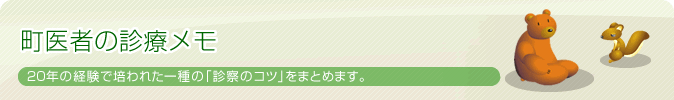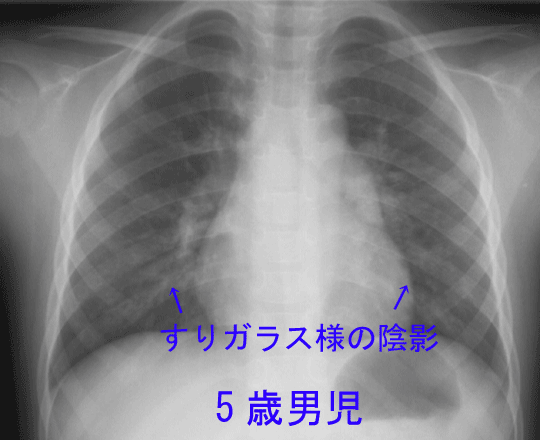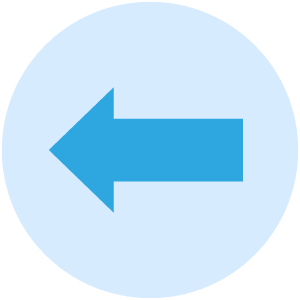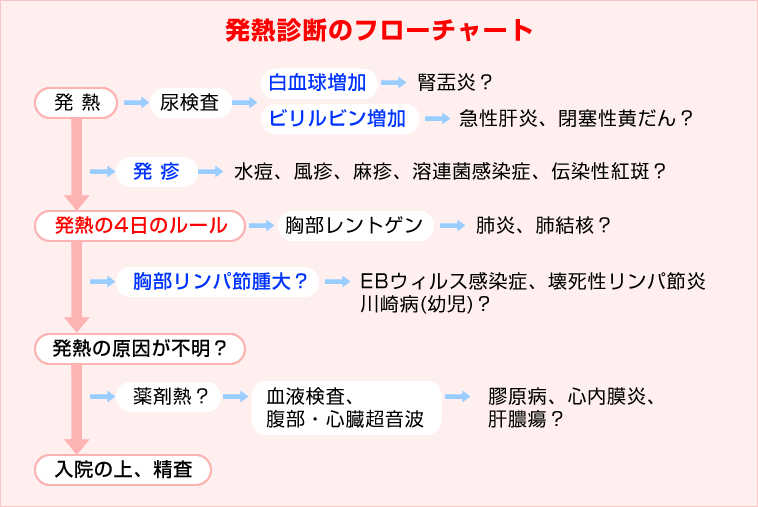4,発熱と咳
かぜの熱は一時的なことが多く、2~3日で下がることがほとんどです。夏かぜやインフルエンザでは、4~5日熱が続いて下がるものもあります。原則として熱が続くときには、「発熱の4日のルール」に従うように心がけます。
こじれているかどうかの判断に役立つのが、「発熱の4日のルール」です。「発熱の4日のルール」では丸々3日は様子をみますが、4日以上熱が続けばこじれていないか、かぜ以外の病気が原因ではないかと疑います。咳がひどいときは肺炎やマイコプラズマ感染症を疑います。
子どもが4日以上にわたり熱が続くときには、内科診療所では子どもの検査が困難なことから、小児科の専門医に紹介を考慮します。いたずらに子どもの熱を引きずっているうちに、結局こじれてしまったという苦い経験が過去にありました。
親の立場からも、子どもの熱が4日以上続けば、こじれていないか?かぜ以外の病気がないかどうか?を疑い、慌て始めなければなりません。咳がひどいときには、肺炎やマイコプラズマ感染症の可能性が高くなります。
反対にいくら熱が高くても咳がないときは、3日以内であれば少し安心して様子をみることができます。昼間の咳に比べて、夜間の咳にはとくに注意が必要です。夜間や早朝の咳は気管支炎のことが多く、熱が出るとこじれやすくなります。
*マイコプラズマ感染症については本サイトをご覧ください。
発熱時には咳以外にも、咽頭痛と嚥下困難(扁桃周囲膿瘍や喉頭蓋炎?)、頭痛(髄膜炎?)、頸部リンパ節腫大(EVウィルス感染症?)、皮膚の変化(発赤、紅斑、水疱など)、尿の異常(腎盂炎?)、心雑音の有無(心内膜炎?)など、診察の上でいくつか注意すべきポイントがあります。
これらは診断の手がかりになるだけでなく、合併症やより重い病気を予防し、早期発見するために重要です。これらについて後から詳しく述べることにします。
咳について
咳はいろいろな病気で起こり、かぜに限ったものではありません。診察室では経験的に、かぜの咳を3種類に分けて考えています。のど(咽頭)からの咳、のどの奥(喉頭)からの咳、気管支からの咳 の3つのどれかを判断するようにしています。
もっとも一般的な咳はのど(咽頭)の炎症による咳。これでは痰がらみの咳が昼間を中心に起こります。咽頭炎とは異なりますが、扁桃炎には注意が必要です。扁桃炎では高熱が出やすいですが、咳はあまり多くありません。しかし、扁桃の炎症が周囲に広がると、扁桃周囲炎、膿瘍を形成すると扁桃周囲膿瘍を起こし、窒息を起こすことがあり大変危険です。
扁桃周囲炎や扁桃周囲膿瘍、次に述べる喉頭蓋炎では、患者の第一声から疑うことが可能です。声が独特のうるんだような、こもったような声になります。
さらに、食べ物や水が飲めるかどうか、つばが飲みにくくないか尋ねます。これらの状態では食べ物はもちろん、水やつばも飲み込むのも困難です。
診察室では口を開けてもらうと確認できますが、そのときに大丈夫でもその夜に急に苦しくなることがあります。危険性が少しでも考えられれば、注意書きや連絡先のメモを渡すくらいの慎重さが大切です。これらの病気では高熱を伴うことはあまり多くありません。
一方、のどの奥(喉頭)が炎症を起こすとケンケンという咳が痰といっしょに起こりやすくなります。声もかれやすくなります。幼児に多い仮性クループもこの咳です。
のどの奥(喉頭)の咳は、「のどの奥の鼻づまり」と考えると分かりやすくなります。かぜで鼻腔が炎症を起こして狭くなると鼻づまりを起こし、息苦しくなります。鼻づまり用の点鼻薬には、少量の血管収縮剤と副腎皮質ステロイドが含まれています。血管が収縮すると一時的に炎症が軽減するため、鼻づまりも改善します。仮性クループでも同じ薬をネブライザー吸入します。喉頭の炎症が速やかに軽減して、息苦しさやケンケンという咳が改善します。
大人では喉頭が比較的広いため、ふつうは喉頭炎が深刻になることはまれですが、喉頭炎は声のかれをしばしば伴います(嗄声、させい)。声帯が炎症を起こすと声がかれてきます(声帯炎)。喉頭炎と声帯炎はしばしばいっしょに起こり、このときはケンケンという咳に嗄声を伴います。
そして喉頭の一部の喉頭蓋が腫れてくると空気の通り道が狭くなり、ひどくなると窒息を起こすためたいへん危険です(喉頭蓋炎と言います)。喉頭蓋炎は口を開けても診断できません。耳鼻咽喉科で喉頭鏡の検査を受けることが必要です。
うるんだような、こもったような声や、食べ物や水が飲み込めるかどうか尋ねることから疑いを抱き、喉頭蓋炎ゼーゼーという呼吸困難を起こす前に、直ちに耳鼻咽喉科を受診する必要があります。
気管支炎の咳の特徴は、就寝前や夜間、早朝の咳き込みです。気温差や気圧の変化(低気圧や台風の季節)が原因で起こりやすく、10人に一人はこのような「気管支が弱い」体質があることが指摘されています。咳ぜんそくと診断されることもあります。咳ぜんそくと呼ばれるように、この咳にはふつうのかぜ薬はあまり効果がありません。一般的なかぜ薬は、咽頭炎や鼻炎を想定しているからだと考えられます。
気管支の咳は、気管支ぜんそくに準じた治療法が効果的なことがあります。気管支の咳に発熱が伴わなければこじれることは少なく、時間がかかっても自然に治ることが多いですが、熱が出てきたときはこじれて肺炎を起こすことがあるので注意が必要です。気管支の咳と熱が出てすぐにこじれて肺炎を起こすわけではありません。こじれているかどうかの判断に、「発熱の4日のルール」が役立ちます。
5,中・高年者の肺炎ではガンに注意
内科診療所では肺炎はごくふつうにみられる病気です。私の診療所では、肺炎を起こしやすいのは子どもや若い年齢層の人たちです。これは多少かぜをひいても、体力にものを言わせて無理をしやすいからだと考えています。
高齢者の繰り返す肺炎の原因の中には、誤嚥性肺炎が多いのではないかと思います。とくに胃の手術をしている高齢者では消化液の逆流が起こりやすく、誤嚥性肺炎を繰り返すことがあります。
中・高年者では、肺炎の原因にガンが潜んでいないか常に注意すべきです。肺がんによる閉塞性肺炎では、ふつうの肺炎とよく似た症状や経過をとることがあります。ガンが肺門部や気管支の中に存在すると、胸部レントゲンでは肺炎像しか示さないことがあります。
このタイプの肺がんは男性の喫煙者に起こりやすく、肺炎がよくなるとガンの存在を見逃す恐れがあります。ハイリスクと考えられる場合では、肺炎が治った後も経過観察を怠らないようにすべきです。必要に応じて胸部CTなども考慮します。
肺炎球菌ワクチンの複数回接種
突然の胸痛で発症する肺炎と言えば、肺炎球菌によるものが知られています。日本呼吸器学会の「成人市中肺炎診療ガイドライン」では、65歳以上の高齢者は肺炎球菌ワクチンを接種すべきとされています。しかし日本での接種率は依然として低く、65歳以上の推定接種率は20%以下です(米国CDCによる2010年の患者調査では61%)。接種率向上のために工夫が必要です。
肺炎球菌ワクチン(PPV23)は、2009年10月からは初回接種から十分な間隔(5年以上)を確保することで再接種が認められています。しかし、10年以上の再々接種、さらに15年以降の接種の可否については議論のあるところです。
複数回接種による副反応については、関節痛、疲労感、頭痛、局所の腫脹、中等度の腕の運動制限が、初回接種よりも多く認められたと報告されています。しかし、初回接種および複数回数接種後30日間における死亡率や重篤な副作用は認められませんでした。
6年以上ごとの反復接種によって、懸念されている複数回接種による低応答は認められず、安全性も容認できるのではないかと考えられます(日本医事新報 No4575、2011.12.31より)。
しかし、国内外を通じて未だワクチンの複数回接種による臨床効果のエビデンスはないのが現状で、今後の検討が必要と考えられます。米国ACIP(予防接種勧奨委員会)は65歳以上の免疫能が正常で、肺炎球菌ワクチン接種後5年以上経過し、かつ前回接種が65歳未満であった場合には再接種を推奨しているものの、それ以降の複数回接種については言及していません。
すなわち、現行の肺炎球菌ワクチンの複数回接種の免疫原性、安全性からは複数回接種は容認できるものの、複数回接種の臨床効果が明確になっていないことから、米国や英国では3回以上の複数回接種を推奨するに至っていないのが現状です。しかし、我が国の平均寿命とワクチンの抗体維持期間を考慮すると、複数回接種は必要と考えられます。
6,若い人の胸痛と胸膜炎
胸膜炎という病気があります。中・高年者では結核などさまざまな病気を疑いますが、若い人ではかぜが主な原因で起こります。若い人が熱もせきもなく、胸とくに側胸部に差し込むような痛みを生じた場合、レントゲンで胸膜炎が原因のことがあります。
肺には痛みの神経がないため、肺炎ではふつうは痛みを伴いません。しかし胸膜という肺を包む膜には痛みの神経が多く分布しています。胸膜に病気を生じると鋭い痛みを伴うことがあります。
若い人の胸痛と言えば、気胸をまず疑います。気胸を疑うときにレントゲンを撮影しますが、気胸は肺の上の部分に起こります。胸膜炎は肋骨横隔膜角(costophrenic angle)という肺の下の部分に起こることがあり、うっかりすると見逃してしまいます。
胸膜炎では熱や咳がほとんどなく、痛みだけが症状のことがしばしばあります。
胸部レントゲンの被曝について
放射線は自然界にも存在します。地球上では場所により差はありますが、大地から1年間に0.46mSv(ミリシーベルト)また、宇宙からの放射線(宇宙線)で1年間に0.38mSv、その他空気からなど1.5mSvほどの被爆を受けます。
それではX線検査による被曝量はどのくらいでしょうか?胸部レントゲンで0.1mSv、胃透視で15mSv、CT検査で20mSv以下程度です。人が白血病やガンになると言われている放射線量は、一度に1000mSvを越える量と言われています。これは胸部レントゲンの被爆量の10000倍です。
妊婦の胎児に対する影響は妊娠時期により異なりますが、おおよそ100mSvを越える量と言われています。1回の胸部レントゲンの被曝量では胎児には影響は及ぼさないことが分かります。しかし、胎児には影響はないとしても、その子孫に及ぼす影響を否定することはできません。妊娠中の安易なレントゲン検査は避けなければなりません。
※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。
※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。