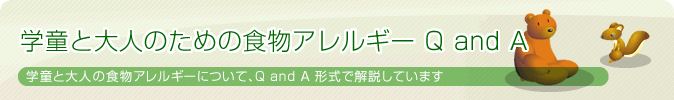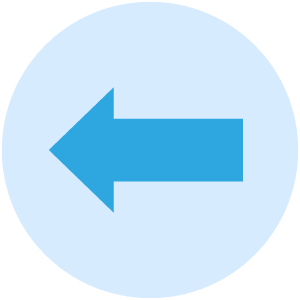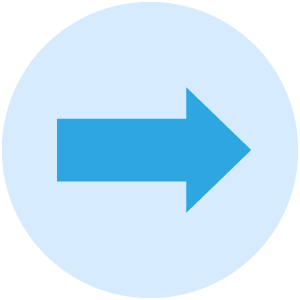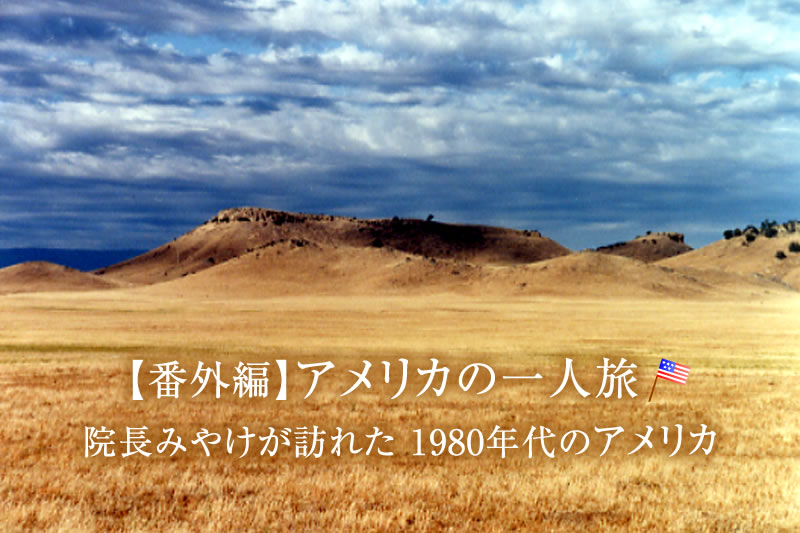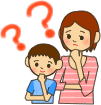 Q3:血中の特異的IgE抗体検査の結果用紙に、0~6までのクラス分けがありますが、どういう意味ですか?
Q3:血中の特異的IgE抗体検査の結果用紙に、0~6までのクラス分けがありますが、どういう意味ですか?
 A3:血液中の食物アレルゲンに対する血中特異的IgE抗体の有無を調べる検査が、血中抗原特異的IgE抗体検査です。ImmnoCAPなど、数種類の測定方法があります。採血が必要になりますが、一度に数種類調べることが可能です。
A3:血液中の食物アレルゲンに対する血中特異的IgE抗体の有無を調べる検査が、血中抗原特異的IgE抗体検査です。ImmnoCAPなど、数種類の測定方法があります。採血が必要になりますが、一度に数種類調べることが可能です。
ImmunoCAPの結果の見方
アレルゲンごとの血液中のIgE抗体の量を分かりやすいように、0~6にクラス分けしています。このクラスの数字が高いほど強く感作されていると考えて差し支えありませんが、陽性ならすべてがアレルギーの原因になっていると判断すべきではありません。
*感作(かんさ)とは、体内にアレルゲン(抗原)が侵入したときに抗体(抗原と結合して アレルギー反応を引き起こすタンパク質)を作ることで、アレルギー反応を起こす準備をすることです。
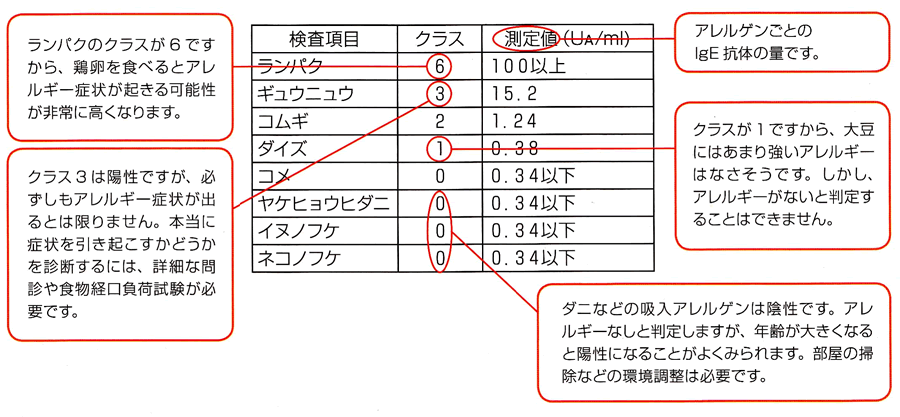
一般に、特異的IgE抗体が高値の時は(RASTスコア3以上)、食物アレルギーを起こす可能性が高いのですが、あまり高値でなければ、食べられる場合もありますし、逆に、抗体値が低値であっても症状が見られることがあります。食物アレルギーを診断する上で、特異的IgE抗体は、確定診断ではなく参考程度と考えた方がよいです。
特異的IgE抗体の測定方法には数種類ありその相関性は高いのですが、中には得られた陰性・陽性の結果が一致しないこともあります。その理由は、各種測定法で用いられているアレルゲンが同じためでないとされています。
したがって、疑わしいのにその特異的IgE抗体が陰性のとき、他の測定方法で再検討することも考慮すべきかもしれません。成長による変化や治療成果などをみるため、経時的な変化を追うときには可能な限り同じ測定法で比較すべきです。
血液検査には好塩基球ヒスタミン遊離試験もあります。これは血中の好塩基球という細胞に抗原を反応させ、アレルギー症状の原因となるヒスタミンという物質が遊離されるかどうかを調べる検査です。
ヒスタミンが遊離されれば、抗原に対するIgE抗体が証明されたことになります。また、ヒスタミン遊離のレベルは、このアレルゲンがアレルギー症状を実際に引き起こす可能性と相関すると考えられています。
即時型は、特異的IgE抗体が検出されることが多く、わかりやすいのですが、ゆっくり型(即時型)では検出されず、診断が難しいこともあります。この場合、食物日誌をつけると原因食物がわかることがあります。
食物日誌とは、毎食どんなものを食べたか記入するわけですが、いつも同じ食品を食べた後に同じような症状が出れば原因食品の可能性が高くなります。
また、除去試験といって、疑わしい食品の摂取を2週間くらい中止してみることがあります。症状の改善(例えば、湿疹がよくなるなど)が、みられれば、その食品が原因の可能性が高まります。
※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。
※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。