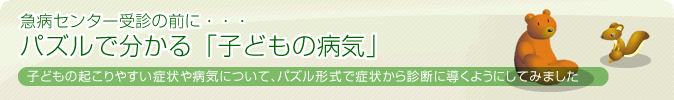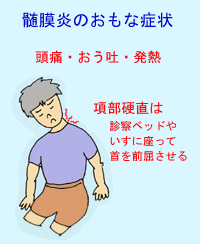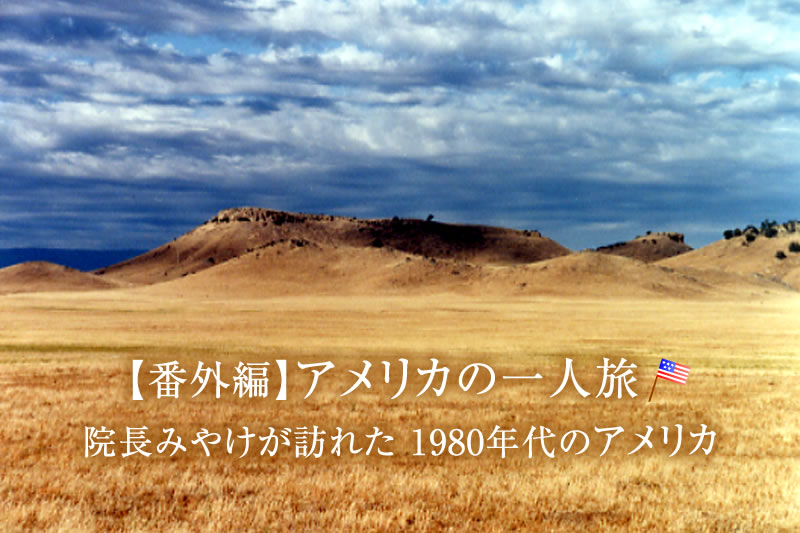熱があるかぜの症状No頭痛やおう吐Yes下痢をしているNo ときは・・・
髄膜炎を考えながら診察を進めていく必要があります。
髄膜炎は大きく細菌性髄膜炎と無菌性髄膜炎(おもにウィルス性髄膜炎)とに分けられます。無菌性髄膜炎の多くは、夏かぜによるもの(エンテロウィルス)とおたふくかぜ(流行性耳下腺炎)に伴うものです。ウィルス性髄膜炎の多くは速やかに回復していくためそれほど怖くありませんが、細菌性髄膜炎は治療に困難を伴うことが多くなります。
また発病の年齢によっても重症度が大きく異なってきます。発病の年齢が低いほど、とくに新生児や乳幼児では診断が困難で、元気がない、哺乳力が弱い、おう吐など母親が何かおかしいと感じる ことが重要な手がかりとなります。
年長児や学童では髄膜炎の3大症状といわれる「発熱、頭痛、おう吐」がみられるようになります。頭痛とおう吐があれば常に髄膜炎を頭に置きながら診察を進める必要があります。髄膜炎の診断には、項部強直といわれる所見が重要視されます。
項部強直とは、髄膜炎などで首の後ろが硬くなり、首を前に曲げにくくなる所見です。自宅で簡単にできる方法としては、足を伸ばして床に座らせ、手を床につけないで自分の力で首を前に曲げさせます。項部強直があるといかにも窮屈そうに首を突っ張った感じになり、同時に背筋に痛みが起こります。このような所見があれば、髄膜炎を疑います。
髄膜炎の診断の困難さは、このような項部強直が分かりにくいこともあるためです。原因不明の発熱が持続するときには、つねに髄膜炎を頭に置く必要があります。
診断のポイント
発熱や扁桃炎がみられなくて、発疹だけで診察に来られたときには、風疹やりんご病と区別が困難なことがあります。このような発疹症は梅雨から初夏にかけて流行してきます。経過をみながら診察を進めることになりますが、それでも分かりにくいことがあります。
区別のポイントは、風疹では首や耳の後ろのリンパ節のはれ、溶連菌感染症はイチゴ舌や手足の指先の皮が薄くむけてくるか?りんご病は手足の発疹に加えて太ももにレース様の発赤が認められるかどうか がなどです。
筆者は発熱は「5日のルール」といって、発熱は4日までは様子をみても(もちろん早くに医師の診察を受けておくのは言うまでもありません)、5日以上発熱が持続するときには、こじれていないか、他に原因がないか、つねに注意しておく必要がある と考えています。
※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。
※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。