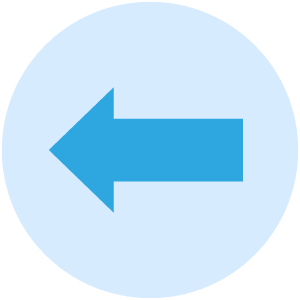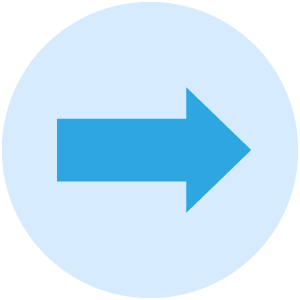- 1.かぜ薬はどんな種類の薬の組み合わせで処方されますか?
- 2.かぜに効く薬はない というのは本当ですか?
- 3.かぜに抗生物質が必要な理由はどうしてですか?
- 4.病院に行くとかぜ薬を何種類も出されるのはどうして?
- 5.かぜ薬は何日くらい飲むものでしょうか?
- 6.薬局のかぜ薬と病院でのかぜ薬の違いは何ですか?
- 7.かぜを引いたとき、どのような場合に病院や診療所に行けばよいですか?
- 8.かぜ薬はきちんと決められたように飲む方がよいのでしょうか?
- 9.かぜ薬を多く飲むと効かなくなりませんか?
- 10.妊娠中にかぜ薬を飲むことができますか?
- 11.妊娠しているのに気がつかずにかぜ薬を飲んでしまいました。大丈夫ですか?
- 12.かぜの予防の薬はありますか?
- 13.かぜのとき、おとなの座薬の使い方は?
- 14.子どもの解熱剤の座薬の使い方は?
- 15.院外処方と院内処方の病院(診療所)がありますが、どうしてですか?
- 16.かぜの筋肉注射は何ですか?
- 17.かぜで点滴はどんなときに行いますか?
- 18.点滴の中には何が入っているのですか?
- 19.かぜの筋肉注射と静脈注射、点滴はどう違いますか?
- 20.注射のあとはよくもんだほうがよいのですか?
- 21.注射器や注射針は清潔ですか?
- 22.のどが痛むとき首に湿布をまいてもいいでしょうか?
- 23.のどにルゴール塗布は効果がありますか?
- 24.抗菌薬(抗生物質)はどのような種類がありますか?
- 25.細菌にはどのような種類がありますか?
- 26.抗生物質の効きにくい耐性菌とはどのようなものですか?
- 27.かぜ薬を飲むと胃が悪くなってしまいますがどうしてですか?
- 28.解熱剤と副作用について?
- 29.抗生物質やかぜ薬によるアレルギーについて教えてください。
- 30.アスピリンとピリンの違いについて教えてください。
- 31.授乳中ですがかぜ薬は飲んでも大丈夫ですか?
・・・
Q1:かぜ薬はどんな種類の薬の組み合わせで処方されますか?
A1:かぜにかかって処方されるくすりはいくつかの種類からなっています。
一般にかぜの治療では現れている症状(たとえば発熱、頭痛、せき、鼻水など)に対してそれぞれの症状を軽くするための薬を組み合わせて処方します。この治療方法を対症治療と言います。
さらにウィルス感染に引き続いて起こりやすい細菌による二次感染の予防目的で、抗生物質を組み合わせて使用します。抗生物質はいろいろありますがその選択にあたっては原因となる細菌を想定しながら一定期間使用し、手当たり次第に漫然と長期間使用すべきではありません。
一方体の抵抗力を助ける目的でビタミン剤や、胃が弱い場合には胃薬を組み合わせることがあります。
病院や診療所で出される薬はいろいろな詳しい検査を経て承認されたものです。このような薬は原則として一つの薬に一種類の内容しか含まれていません。市販薬の多くが一つの薬の中に多数の内容が含まれているのと大きな違いです。
このような理由から何種類もの薬が出される結果となります。処方される薬は医師の判断によって多少異なりますが、3,4種類の薬が出ることが多いと思われます。
Q2:かぜに効く薬はない というのは本当ですか?
A2:かぜをひいて診療所などを訪れたときに処方される薬は、それぞれの症状によって医師の判断によって異なってきます。
ふつうは対症療法といって、せきや鼻水、発熱や頭痛などそれぞれの症状に対して、それらを軽くするための薬を組み合わせて処方します。さらにかぜがこじれて細菌によって攻撃されないように抗生物質が投与されることがあります。また体の抵抗力や回復力を助けるためにビタミン剤が投与されることがあります。
かぜの多くはインフルエンザのようにウィルスが原因で起こってきます。しかしかぜのウィルスに直接作用して増殖や活動を押さえる薬(抗ウィルス薬)はほとんどなく、かぜに効く薬はないと言われるゆえんでしょう。
インフルエンザに対しては抗ウィルス薬が開発され使用されています。インフルエンザウィルスが体内に入りこんで活動を始めた初期に内服すると、著しいウィルス増殖を抑える働きがあります。
その結果、内服して1,2日後には解熱するなど著明な効果がみられます。
Q3:かぜに抗生物質が必要な理由はどうしてですか?
A3:かぜのほとんどがウィルス感染症なのでみだりに抗生物質を乱用すべきでない との意見があります。
ウィルスによる気道感染症は呼吸器ウィルスとの一対一の戦いではありません。気道には少数の細菌が存在し、また呼吸とともに常に微生物が吸入されていて、気道の防御機能は休みなく働いています。言い換えれば気道は常に外敵の侵入に対して緊張状態を保ち続けています。
かぜなどのウィルス感染が起こると、その防御機能も破壊されることになり、細菌による攻撃を受けやすくなります。これが二次感染と言われるものです。
抗生物質の利用はかなりの頻度で細菌性肺炎の予防に役立っているものと考えられます。
抗生物質の使用が気道の正常細菌群を抑制し、耐性菌の定着を起こしやすくしているという意見もありますが、一般外来での数日間の抗生物質の使用ではこのような現象はみられません。
しかし抗生物質の乱用はよくありません。かぜにおいて抗生物質使用にあたって、二次感染を起こしそうな病状と原因となる細菌を想定しながら一定期間使用すべきと思われます。
Q4:病院に行くとかぜ薬を何種類も出されるのはどうして?
A4:本コーナーのQ1とA1をご覧ください。
Q5:かぜ薬は何日くらい飲むものでしょうか?
A5:病院や診療所で処方される薬には、医師の判断により対症療法のための薬(発熱、頭痛、せき、のどの痛み、鼻水など、かぜの主な症状を軽くするための治療)と抗生物質が主なものです。
場合によってはビタミン剤や胃薬が加えられます。この中で対症療法のための薬は症状が軽くなれば、内服の回数を減らしたり途中で止めることも可能です。
ふつうは数日でかぜの症状は軽快することが多いと思われます。
これに対して抗生物質は細菌による二次感染を予防したり、すでに起こっている細菌感染を治療する目的で使用されます。抗生物質が有効に作用するためには一定以上の血中濃度が維持されている必要があります。そのためには抗生物質は決められたとおりにきちんと飲む必要があります。
しかしすべてのかぜの症状に抗生物質が必要なわけではありません。抗生物質の乱用は控えるべきでしょう。
Q6:薬局のかぜ薬と病院でのかぜ薬の違いは何ですか?
A6:薬局で買うかぜ薬の内容をみると、多くの場合数種類の薬が含まれているの気がつかれるでしょう。
これらは主にかぜの症状(発熱、頭痛、せき、のどの痛み、鼻水など)に対する成分で、それらを軽くするため数種類の成分が混ぜ合わされています。市販薬は皆様に興味を持ってもらい、買ってもらわなければなりません。そのためにいろいろと工夫もこらされています。
医師により出されるかぜ薬も症状に対する治療が主なものですが、それらの薬の多くはのどや鼻、気管支などの生理的な機能を詳しく研究した結果生み出されたもので、非常にレベルの高い薬です。市販薬と異なり、医師によって処方される薬のほとんどは、一剤に一種類の成分が原則です。
すなわち市販薬はかぜの症状を軽くすることを主眼に置いて作られていますが、医師によって使用される薬はかぜや体の構造の理論に基づいて作られている薬と言えるでしょう。
抗生物質の多くも(膀胱炎の抗生物質は市販されています)、医師によって処方されます。
解熱剤や鎮痛剤は市販薬にもアスピリン、アセトアミノフェンなど優れたものがありますが、最近これらの薬による副作用(インフルエンザの脳炎、ライ症候群など)が医薬品でも問題になっていますので、充分気をつけて使用すべきでしょう。
Q7:かぜを引いたとき、どのような場合に病院や診療所に行けばよいですか?
A7:かぜ(感冒)はかぜ症候群ともよばれるように、病名ではなくさまざまなかぜ症状の総称といえます。
かぜの炎症の主役となっている部位から、のどから気管支にかけてそれぞれ、急性上気道炎、急性扁桃炎、急性咽頭炎、急性喉頭炎、急性気管支炎、気管支肺炎、肺炎などと呼ぶのが正確な病名といえます。
市販薬のほとんどの薬の効能がせき、鼻水、くしゃみ、のどの痛みなどとなっています。これらはかぜ症状の中心が鼻、のどに限られている症状といえます。これらはかぜ症状の初期症状と思われ、このような軽いかぜの症状の時には市販薬も効果的と思われます。私たちのかぜと呼ぶ症状の多くは、このような軽い急性上気道炎が中心であるのも事実です。
しかしこれらの症状が少し長引いてくるといろいろな合併症が起こりやすくなります。
小児では急性中耳炎や結膜炎が起こりやすくなったり、急性副鼻腔炎が起こることもあります。またせきが長引くと喘息発作のように激しくせき込みたいへん苦しくなります。また発熱が続くと肺炎などが起こることがあります。
大人でも同様のことが起こりますが、かぜがこじれて肺炎や心臓の病気(感染性心内膜炎、心筋炎など)を引き起こしたり、かぜと思っている症状が全く別の内科的な病気が原因のこともあります。
かぜの症状が単なるかぜの症状か、またはこじれていないか、それとも別の病気が原因ではないかどうかは自分では判断できないことがほとんどです。かぜをひいて市販薬を飲み、2,3日たっても良くならないときには、医師の診察を受ける方がよいでしょう。
Q8:かぜ薬はきちんと決められたように飲む方がよいのでしょうか?
A8:かぜ薬の多くは鼻水やくしゃみ、のどの痛み、せき、発熱などの症状を軽くするために使用され、このような治療は対症療法といわれます。
それに対して抗生物質や喘息に対する気管支拡張薬、気管支炎の予防のための去痰剤などは決められたように定期的に飲むことにより、薬の血中濃度が維持されて効果が出てくるものも多くあります。
熱が下がってくれば解熱剤は使用を止めていくように、対症療法は症状が良くなってくれば止めることができるものがほとんどです。市販薬の多くは対症療法が中心なので良くなれば、止めることができます。
一方、医師によって処方される薬はかぜ症状を軽くするための対症療法の薬と、抗生物質などのように薬の血中濃度が維持されて効果の出る薬があります。病院の薬のほとんどは、体のしくみを解明し、使用されるまでに多くの試験的な使用を経て造られたものです。したがって体の生理的なしくみに直結する薬なので、規則正しく内服してはじめて効果が出てくるものがほとんどです。
最近は薬の種類や飲み方について詳しく説明をすることがふつうになっているので、診察室では薬の飲み方について良く確認をしておきましょう。
Q9:かぜ薬を多く飲むと効かなくなりませんか?
A9:医師により処方されるかぜ薬には鼻水、くしゃみ、せき、のどの痛み、熱など今ある症状を軽くするための薬(これを対症療法といいます)と、抗生物質などのように治療や予防目的で使用される薬に分けられます。
医師により処方される薬の多くは、一剤に一種類の薬の成分が含まれることが多く、対症療法の場合には2,3種類の薬が処方されることが多くなります。それに加えて抗生物質が一種類出されることが多く、合わせるとかぜ薬として3,4種類処方されることが多くなります。
対症療法薬は症状を軽くするための薬であり、長期間服用したからといって効かなくなることは考えにくいでしょう。しかし3,4日飲んでも効果がみられないときには、いたずらに同じ薬を飲み続けるのではなく、変更したりこじれていないかもう一度診察を受けるのが望ましいと思われます。
抗生物質の乱用は、原因となる細菌が抗生物質に対して効かなくなる(耐性菌といいます)ことがあり慎むべきです。しかし耐性菌の多くは、病院内で長期間にわたり多量の抗生物質を点滴などにより投与された場合に起こりやすいと考えられます。
一般の診療所でかぜ薬として出される数日の内服薬程度では、抗生物質に対して耐性菌は生じにくいと考えられています。
要はかぜ薬を飲み続けても効かなくなることはないと思われますが、あまり効果のない薬を飲み続けることは意味があるとは思えません。しかし、薬には喘息の予防やある種の肺炎などの予防目的で処方されることも多く、医師から薬の説明をよく聞いておくべきでしょう。
Q10:妊娠中にかぜ薬を飲むことができますか?
A10:かぜ薬に限らず多くの薬の注意として、妊娠の可能性のある女性は薬を飲むことを控えるように書いてあります。
妊娠中にかぜをひいても薬が一切飲めないかというとそうではありません。漢方薬や安全な薬を組み合わせながら処方することができます。
妊娠中の女性にかぜ薬を出すときの医師の注意としては、できるだけ主治医の産婦人科医の了解を得た上で、薬を出すべきと思われます。これは出産は、妊産婦と産婦人科医との間でかわされた一種の契約と考えられるからです。
一方的に内科医がかぜ薬などを出すのは、この契約に影響を及ぼすことになり、好ましくないと考えられます。内科医として安全性がはっきりしない薬を処方するときには、主治医の産婦人科医に問い合わせるのが望ましいと思われます。
また、患者としては薬に不安があるときには、飲む前に産婦人科医に問い合わせてみるのもよいでしょう。
多くの産婦人科の医師は妊娠7ヶ月を過ぎると胎児の成長が完成してくるため、ほとんどのかぜ薬を安全に使用することができると説明されます。しかしこれは主治医の産婦人科医によって意見が異なると思われますので注意が必要です。
また、解熱剤の座薬は胎児に影響を与えることがあり、出産後までは使用は控えるべきです。
薬の中での吸入薬や点媚薬、点眼薬などの外用薬は局所だけに作用するものが多く、妊娠中も安全に使用できるものが多くあります。これらの薬を利用するのも方法の一つです。
出産までの長い期間はそれでなくても神経質になりやすい時期です。薬のことで余分な心配をしないように、医師と相談をしながら慎重に薬を飲むべきでしょう。
Q11:妊娠しているのに気がつかずにかぜ薬を飲んでしまいました。大丈夫ですか?
A11:妊娠を知らずにうっかりかぜ薬などの薬を飲んでしまうのはしばしば起こり得ると思われます。
妊娠に気がつくのは月経の予定日を過ぎてから1,2週たってからが多いでしょう。受精をしてから妊娠に気がつくまでの3,4週間は受精卵はどのような発育段階にあるのか考える必要があります。
受精後、受精卵は細胞分裂を繰り返しながら卵管の中を子宮に向かって移動していきます。約1週間かかって卵管を移動し、子宮に到着します。このころの受精卵は胎芽といわれ、胎児になる内細胞群と胎盤や血管になる外細胞群とに分かれていきます。
そして3週目ころに子宮内にもぐりこみ、着床したことで妊娠が成立します。着床した受精卵は子宮に固定され、分裂を繰り返し、4~5週後になると胎芽は小さな魚のような形になります。
この時期は器官形成期と呼ばれ、からだの主な器官ができはじめる大切な時期です。たとえば、脳や心臓、手足、目、耳などはこの月の前半に現れ始めます。さらに内臓も分化を始めます。
約8週を過ぎると胎芽から胎児と呼ばれるようになり、だんだん人間らしい形になってきます。
このように受精卵が胎芽となり、からだの器官が分化し始めるのは約4週以後で、この時期からが薬の影響を考える上で大切な時期といえるでしょう。
妊娠に気がつくのはこの4週目くらいが多いと思われます。4週目までは受精卵は器官形成の準備段階で、かぜ薬などの影響は受けにくい時期と考えられます。したがって妊娠を知らずにうっかりかぜ薬を飲んでもそれほど心配はいらないと思われます。
しかし出産までの長い期間を薬の心配をしながら過ごすのは好ましくないでしょう。妊娠の可能性のあるときには、初めから薬を避けるようにするべきでしょう。
またやむを得ず薬を飲むときには、妊娠を避けるなど計画的に考えるようにしましょう。
Q12:かぜの予防の薬はありますか?
A12:かぜの90%以上はウィルスが原因で起こってきます。かぜの症状を引き起こすウィルスは200種類以上あり、これらのウィルスの感染を予防する薬は残念ながらありません。
抗生物質は細菌感染を治療するための薬で、細菌による二次感染を予防する働きはありません。したがっていくら抗生物質を予防目的で飲んでいても、かぜを引きますし、細菌による二次感染を起こすことがあります。
インフルエンザウィルスに対しては抗ウィルス薬があり、インフルエンザの感染に対して治療目的で使用されます。かぜではありませんが、ヘルペスウィルス感染症に対してウィルスの増殖を抑える抗ウィルス薬があります。
ウィルスの増殖を抑え、治療目的で使用される抗ウィルス薬は、これらの2種類のウィルスに対するものです。しかしこれらの薬も予防目的で使用することはできません。
非常に高価な上、予防効果があいまいなだけでなく、くすりの乱用はウィルスがこうした薬に対して耐性を獲得し、効かなくなる恐れがあるからです。
インフルエンザの予防には予防接種がもっとも有効です。また細菌性肺炎を引き起こしやすい肺炎球菌に対しても予防接種があります。予防の目的で行うにはこれらの予防接種がもっとも有効です。
結局、かぜのためにはふだんの生活の中での注意が肝心で、すべてのかぜを有効に予防する薬は存在しません。
Q13:かぜのとき、おとなの座薬の使い方は?
A13:座薬は大人ではおもに痛みを軽くする目的で使用されます。
一方、座薬は熱を下げるためにもたいへん役にたちますが、その使用に際しては注意が必要です。
高齢者で解熱の目的で座薬を使用したときに、急に血圧が下がって怖い思いをすることがあります。やむを得ず高齢者に座薬を使用するときには、量を子どもの量に減らす(大人の量の半分だけ使う)などの配慮が必要です。
座薬を解熱目的で使うと、多量に発汗してきます。そのあとに汗で体が冷えてしまわないように、衣服を着替えましょう。
座薬の使い方についてですが、夜寝る前に使用するのが便利です。熱が下がり安眠できるようになりますが、汗がでるため着替えを枕元に用意しておくと便利です。日中は飲み薬で解熱剤が出されているときには、座薬の使用は控えるべきでしょう。一日の使用量は2個くらいにしておきましょう。
Q14:子どもの解熱剤の座薬の使い方は?
A14:子どもでは座薬は使いやすいため、熱を下げる目的でしばしば使用されます。
現在、子どもに使用される座薬は、アセトアミノフェン(商品名アルピニー座薬など)、イブプロフェン(商品名ユニプロン座薬など)、ジクロフェナク(商品名ボルタレン座薬など)です。一般に、小学生まではおもにアセトアミノフェンかイブプロフェンが使用され、小学生になるとジクロフェナクも使用されるようになります。
ときにジクロフェナクを5,6歳までの子どもに使用することがあります。この薬はかなり強力な解熱作用がありますが、次の理由から子どもには使用を控えるべきと思われます。
インフルエンザ脳症の原因の一つとして、ジクロフェナクなどの解熱剤との関係が深く考えられています。インフルエンザではジクロフェナクの使用は禁止されていますが、家庭ではインフルエンザとかぜの区別は困難で、誤って使ってしまう危険性があります。要するに、このような危険性のある薬は家庭に保管しておかないことです。そのためには医師が処方するのを控えるべきでしょう。
私見として、ジクロフェナクは小学生を含めて小児では使用しない方がよいと考えています。アセトアミノフェンとイブプロフェンは安全な薬と考えられています。
最近の研究では発熱はからだに有利に働いているとの考え方が優勢になっています。無理に熱を下げるとかえって、かぜと戦うからだの働きを抑え、長引くことになるかも分かりません。
また解熱剤のさまざまの副作用や合併症の問題が明らかになってきました。子どもが発熱にもかかわらず元気の良いときには、座薬など解熱剤の使用は最小限にするべきでしょう。
逆に高熱のためぐったりとして元気のない時や、熱性けいれんなどで座薬を指示されているときには、使ってもよいでしょう。
親の立場からすると、小さな子どもが熱で苦しんでいる様子をみると、一時も早く熱を下げてあげたいという気持ちになるのも当然でしょう。しばしば、座薬を使っても熱が下がらないという苦情を聞かされます。
熱は時期がくれば自然に下がるものです。また熱はこじれて肺炎を起こしていないか、他の病気を合併していないかなどの大切な兆候です。むやみに熱を下げようとするのはどうかと思われます。
小さな子どもにジクロフェナクのような強い座薬を使うと、熱が下がりすぎて冷たくなって怖い思いをすることがあります。このようなことがないように配慮しましょう。
Q15:院外処方と院内処方の病院(診療所)がありますが、どうしてですか?
A15:医薬分業の立場から、院外処方が政策的にも進められてきました。
しかしここにきて院外処方を進める声が少し弱くなってきた感があります。それは院外処方の長所と欠点が明らかになってきたからと思われます。欧米では完全に医薬分業となっていて、院内で薬を出されることはありません。
院外処方では、薬剤師により服薬指導がきちんと行われ、医師の処方もチェックされるという大きな長所があります。本来、薬のことは専門の薬剤師が管理を行うのが当然といえるでしょう。
しかし、日本では医薬分業が進められるにつれて、薬局が病院(診療所)のごく周囲に建てられるようになってきました。欧米のようにどこの調剤薬局でも薬をもらえるはずですが、当然のことながら隣接する薬局に行って薬をもらうことになります。圧倒的に隣接する薬局が有利です。
さらに、病院や診療所の立場からすると、院外処方箋を発行するほうが、院内で薬を出すよりも圧倒的に経営的に有利です。患者側からすると、院外処方ではわざわざ薬をもらうために別な薬局に行かなくてはならないこと、余分な料金が必要なことなどの不便があります。
このような理由から医師の間でも、医薬分業に関して意見が二分されるようになってきました。
ここで医薬分業(院外処方)について多くの私見を述べることは控えますが、いずれにしても「院外処方」が「院外商法」にならないようにすべきでしょう。
Q16:かぜの筋肉注射は何ですか?
A16:かぜの時に受ける筋肉注射には、解熱剤と抗生物質が考えられます。
発熱時には解熱剤を注射すると一時的に熱が下がってくるために楽になるでしょう。しかしこのような解熱剤はピリン系の解熱剤でピリンアレルギーが問題となります。
ピリンアレルギーはたいへん怖いものでショックを起こして、急に心停止を起こしたり呼吸困難を生じてきます。ピリンアレルギーがあるかどうか、本人の記憶があいまいなことも多く、かぜの治療にこのような危険な治療を選ぶ理由は少ないと思われます。
抗生物質の筋肉注射が行われることもあります。筋肉注射の場合には血中濃度が比較的長く維持されるために、効果が持続されやすい利点があります。それでも効果は数時間程度と考えられ、細菌による二次感染の予防にどの程度役にたっているか疑問があります。
かぜは90%以上がウィルスが原因で起こってきます。抗生物質はウィルスには無効なのでかぜの初期に抗生物質の注射をするのでは効果は期待できないでしょう。少なくとも2,3日経過して二次感染を起こして、こじれかかっているときに行うべきでしょう。
以上の理由から筋肉注射の危険性や効果が疑問視されるために、筋肉注射は最近はあまり積極的には行われなくなってきました。
Q17:かぜで点滴はどんなときに行いますか?
A17:点滴は大きく分けて1)補液目的で行う場合と、2)抗生物質の投与の目的 で行う場合とが考えられます。
かぜをひいて点滴を受けると、とたんに体が楽になるのをよく経験します。正確な理由は分かりませんが、おそらくかぜをひいて食欲が落ちて軽い脱水状態になっていて、この脱水状態が改善されるためと考えられます。
さらに補液を行うことによって体のホメオスターシス(恒常性:からだの働きをもっとも良好な状態に保とうとする自然回復力)を刺激するためかも分かりません。補液の目的で点滴を行うときには、多くの場合にはビタミンBやビタミンCが混合されます。かぜをひくとビタミンの消費量が増加するために、点滴でビタミンを補給することもできます。
しかし、まれにビタミン注射でもアレルギー反応を起こすことがあるので注意が必要です。
さらにかぜがこじれて細菌による二次感染が疑われるようになると、点滴の中に抗生物質を入れることがあります。抗生物質の内服に比べて、点滴による投与は血中濃度が上昇しやすくより効果的です。
抗生物質の投与を行うときに大切なのはタイミングで、早期から抗生物質の投与を行う必要はないものと思われます。かぜのほとんどはウィルス感染が原因で起こりますが、ウィルス感染に対しては抗生物質の投与は効果はありません。抗生物質が効果的なのは、二次感染を起こしかけている数日後からと思われます。
病気の症状(病態)を考えながら抗生物質を使用するかどうか決めるべきで、抗生物質の乱用は耐性菌の出現を起こしやすくするために控えるべきです。
Q18:点滴の中には何が入っているのですか?
A18:点滴本体の内容には2つの重要な点があります。
第一は血しょうとほぼ同じ浸透圧を持ち、さらに血液中の電解質バランスを大きく崩すことがないようにすること、第二は血液中の酸・塩基(pH)を一定に保つ働き-緩衝作用-を持たせること の2つです。
血しょうにはタンパク質をはじめさまざまの物質が溶け込んでいるために、かなりの濃度があります。血しょうと血球成分やからだの組織との間に濃度差が生じるとこれを一定に保とうとする圧力が生じます。これを浸透圧とよび、からだの恒常性(ホメオスターシス)を保つための一つの因子になっています。
血液中に大量の水分を入れると、血液が希釈されるために血しょうと血球や組織の間に濃度差を生じることになります。こうなると血球や組織の破壊が起こることになりたいへん危険です(水中毒)。血しょうと点滴との間に浸透圧の差ができるだけ少なくなるように点滴の内容は工夫されています。
そのため点滴の中にはさまざまの電解質やブドウ糖が含まれ、血液中に入ったときに血液成分との間に大きなバランスの崩れを生じないようになっています。
しかしふつうに行う点滴では、タンパク質や脂肪の補給はできません。またブドウ糖の量も少なく、点滴で補給できるカロリーはせいぜい100~200キロカロリーで、ほぼごはん一膳程度です。
出血やショックなどで大量の補液を必要とするときには、血清ナトリウム濃度と同じ濃度を含む点滴を選択します。このような点滴には血液のpHのバランスを崩さないように、緩衝作用を持つ物質が含まれている場合があります。
しかしふつう病院(診療所)の外来で行われる点滴ではあまり高濃度のナトリウムが含まれない種類の点滴が使用されます。
食事が長期間とれない場合には、高カロリー輸液が行われます。高濃度のブドウ糖やタンパク質の点滴が行われますが、これらの点滴を手足の静脈を使うと激しい痛みを感じたり、すぐに静脈が詰まってしまいます。
そのため点滴のチューブを心臓近くに留置すると、長期間にわたり高濃度の輸液を行うことができます。中心静脈栄養と呼ばれますが、細菌などが混入しないように点滴チューブにフィルターを置くなどの注意が必要で、厳重な管理が求められます。
Q19:かぜの筋肉注射と静脈注射、点滴はどう違いますか?
A19:かぜの治療に注射が必要かというと必ずしもそうではありません。
注射が必要になるのは、倦怠感や発熱、おう吐、げりなどが続いて食事があまりとれなくなったときや、かぜがこじれかかって細菌による二次感染を起こしはじめたときと思われます。
筋肉注射は解熱剤や抗生物質がおもな内容です。解熱剤の注射はピリン系のものになりますが、体質によってはピリンアレルギーが起こることがありたいへん危険です。抗生物質の筋肉注射が行われることがあります。
抗生物質の種類によっては、注射をうつ前にアレルギー反応が起こらないかをチェックするために、テストを行うように指示されています。抗生物質の注射にはアレルギーテストの必要のないものもあり、簡便性もあり外来ではこれらの種類の注射が選択される場合がありますが、実際に効果があるかどうかは疑問です。
抗生物質の筋肉注射は静脈注射に比べて血中濃度が低いため効果は劣りますが、筋肉から徐々に血液中に入るため、効果が持続しやすい利点があります。
静脈注射と点滴は分けて考える必要があります。静脈注射で行われる主な内容はブドウ糖とビタミン剤だと思われます。場合によっては肝臓を守るための保護剤が混合されることもありますが、医師によってその内容はまちまちです。
ブドウ糖とビタミン剤の静脈注射がどの程度効果があるのかは、個人差がありはっきりしていません。食事がとれないときや発熱時にはビタミンの欠乏状態があると考えられ、その補給は意味があるといえますが、逆に昔から習慣的に行われてきたともいうことができます。
注射や点滴をして気分的に楽になったと感じる人も多いことでしょう。しかし実際に効果があるかどうかははっきりとしていないようです。
Q20:注射のあとはよくもんだほうがよいのですか?
A20:本HPをご覧ください。
健康いろいろQ&A-インフルエンザ-Q9
Q21:注射器や注射針は清潔ですか?
A21:現在、診療所や病院などで使用されている注射器や注射針はすべて使い捨ての清潔なものが使用されていると推測されます。
B型、C型肝炎ウィルスなどは血液を介して感染する可能性があり、煮沸消毒やオートクレーブ消毒などで注射器や注射針を再利用することは厳に慎まなければなりません。
その昔、使い捨ての医療機器が一般的でなかったころ、煮沸消毒などで注射器や注射針を繰り返し使用していた時代がありました。現在、中高年者のC型肝炎の蔓延の一つの原因になっているのではないでしょうか?
しかし最近でもまれに特定の医療機関でB型肝炎やC型肝炎が多発することがあります。十分に注意の上、注射などが行われていると思われますが、点滴や人工透析などで血液に直接接触しないと思われるときには、同一の注射器が繰り返し使用されることがあります。
血液の混入の可能性が少しでも考えられるときには、そのつど新しい注射器を使用すべきでしょう。
Q22:のどが痛むとき首に湿布をまいてもいいでしょうか?
A22:のどの痛みやはれぼったいときに、関節の痛みや筋肉痛に使用する湿布を使用することは控えた方がよいでしょう。
湿布は首やのどに使用すると冷たく感じたり、すっとするために気持ちよく感じることがあります。しかし湿布の表面にはさまざまな薬がぬってあります。その薬が皮膚を通して浸透していき、関節や筋肉の炎症を抑える働きがあります。
のどの炎症のときにも湿布を使用すると炎症を抑える働きが予測されますが、ときに湿布の薬のために炎症部位の血管が拡張し、炎症がいっそう強くなることがあります。とくに扁桃周囲膿瘍や喉頭炎では炎症が強くなると、気道が細くなり呼吸困難を生じることがあり危険です。このような理由から、耳鼻咽喉科の医師も湿布の使用は控えるべきであると言われます。
湿布剤と異なり、子どもの発熱時に使用される冷却用のシートは、熱を奪い去るだけの効果のため、安全に使用できると思われます。
Q23:のどにルゴール塗布は効果がありますか?
A23:ルゴールにはヨウ素とヨウ化カリウムが含まれ、のどの消毒や殺菌目的で古くから使用されてきました。
かぜをひくと昔からのどにルゴールを塗ることがしばしば行われてきました。独特のニオイがあり、記憶されている方も多いでしょう。
ルゴール塗布は現在でも耳鼻咽喉科では広く使用されていますが、内科ではあまり使われなくなってきました。その理由は明らかではありませんが、ニオイがいやがられたり、おう吐反射が起こったり、さらにヨードアレルギーの可能性、多量に使用すると甲状腺の働きを抑える などの理由が考えられます。
ヨードには強い殺菌作用があり、その液体は手術の際に皮膚の消毒に広く使用されています。またうがい液やスプレーが一般にも広く使われています。しかし一回だけのどに塗布しても、すぐに効果が消えてしまい持続的な効果は期待できないでしょう。
抗生物質の内服が一般的になってから、ルゴール塗布はしだいに行われなくなってきました。
Q24:抗菌薬(抗生物質)はどのような種類がありますか?
A24:抗菌薬(抗生物質)は細菌などの病原体に静菌的にあるいは殺菌的に作用する薬剤で、微生物によって生産される抗生物質、現在ではほとんど化学合成されている抗生物質、純粋に化学合成だけされている合成抗菌薬 などがあります。
抗生物質という場合には、βラクタム薬とアミノグルコシド薬、マクロライド薬などがあります。合成抗菌薬にはキノロン薬、新キノロン薬などがあります。この中で現在もっともよく使用されているのは、βラクタム薬(ペニシリン薬、セフェム薬など)とマクロライド薬、新キノロン薬です。
βラクタム薬は殺菌的に作用するものが多く、現在もっともよく使われています。この中でペニシリン薬は古くから使用されてきましたが、耐性菌の出現やペニシリンアレルギーなどの問題から、セフェム薬の開発後は使用される機会は少なくなってきました。
セフェム薬は注射でも内服でも現在もっとも多く使われています。セフェム薬は比較的広い範囲の細菌に有効であるばかりでなく、ペニシリンのような強いアレルギー反応が起こりにくいため使いやすい抗生物質です。
マクロライド薬は静菌的に作用し、おもにグラム陽性菌(小児や一般の成人でかぜなどがこじれる原因となる菌のグループ)に効果がありますが、その40~50%は耐性といわれています。
しかし耐性菌以外の菌にはいぜんとして強力に作用し、とくにβラクタム薬の効果が少ないマイコプラズマやクラミジアなどの感染症によく使われます。胃・十二指腸潰瘍の原因と考えられているヘリコバクター・ピロリ菌に対しても有効です。
新キノロン薬は広い範囲の細菌にもっとも強く作用するために、現在セフェム薬とともに多用されています。今までの抗生物質が効きにくかったグラム陰性桿(かん)菌に作用し、難治性慢性気道感染症や尿路感染症、腸管・胆道感染症などに対してある程度内服で治療が可能になってきました。
ただしよく使われるため、耐性菌の出現が心配されています。
これ以外にもセフェム薬の新世代薬や、βラクタム薬の改良された薬(カルバペネム薬、モノバクタム薬、ペネム薬)などが開発されてきました。このような薬は従来の抗菌薬が効きにくかった難治性細菌感染症に対して使用されるもので、一般の外来感染症に対して必要な薬であるとは必ずしもいえません。
今後、耐性ぶどう球菌(MRSA)のように有効な抗菌薬が少ない細菌が増えてくると、どのような恐ろしい事態になるか想像もできません。抗菌薬の乱用は耐性菌の出現からも厳に慎むべきでしょう。
Q25:細菌にはどのような種類がありますか?
A25:細菌を分類するために1884年グラムによって考案された細菌染色法による分類が現在もなお利用されています。
グラム染色によって染まる群(グラム陽性菌)と染まらない群(グラム陰性菌)とに大きく分類されます。グラム陽性菌の多くは形が球形をしているためにグラム陽性球菌と呼ばれ、ブドウ球菌、レンザ球菌、肺炎球菌などが含まれ、一般の外来の細菌感染症としてなじみの深い細菌群です。
グラム陽性菌は細胞質膜の外側に細胞壁を持つだけで、グラム染色により黒紫色に染まってみえます。グラム陽性菌に対しては抗菌剤の多くが効力を持っていましたが、耐性菌が出現してきて抗菌薬の選択に苦慮することがあります。
グラム陰性菌の多くは棒状の形をしているためにグラム陰性桿菌と呼ばれ、大腸菌、インフルエンザ菌(インフルエンザウィルスとは異なります)、緑膿菌などが含まれます。グラム陰性桿菌の多くは抵抗力の弱った状態で増えてくるため、難治性で抗菌剤が効きにくいために治療に困難を伴います。グラム陰性菌は細胞壁の外側にさらに外膜を持っています。
新しく開発されてきた抗菌剤の多くが、グラム陰性桿菌に対して抗菌力を持つように改善されてきました。しかし新しい抗菌薬が登場すると新たに耐性菌が出現してくるなど大きな問題点を抱えています。
細菌やウィルスに分類されない感染症には、マイコプラズマ、クラミジア、レジオネラなどによる感染症があります。これらによる呼吸器の感染症は一般によく使われるβラクタム薬(ペニシリン薬、セフェム薬)に抵抗性を示すため、マクロライド薬やテトラサイクリン薬の薬が選択されます。
Q26:抗生物質の効きにくい耐性菌とはどのようなものですか?
A26:次のホームページをご覧ください。
https://amr.ncgm.go.jp/general/1-2-1-1.html
Q27:かぜ薬を飲むと胃が悪くなってしまいますがどうしてですか?
A27:かぜ薬による胃腸障害の原因としてはおもに抗生物質によるものと解熱剤によるものとが考えられます。
抗生物質による胃腸障害の多くは口腔内や腸内に存在する常在菌叢のバランスが崩れて起こってきます。
私たちの腸内には膨大な数の細菌が住んでいます。この中にはからだに有益な善玉菌、有害な悪玉菌、善玉にも悪玉にもなる日和見菌の三種類が存在します。善玉菌の代表が乳酸菌とビフィズス菌です。悪玉菌は腐敗菌ともいわれタンパク質や脂肪を腐敗させ、さまざまな有害物質を作り出します。
長期にわたる抗生物質の内服は善玉菌も殺してしまうため、善玉菌が減少し胃腸障害だけでなく、さまざまな障害を起こすことがあります。たとえばビタミンB2の吸収には腸内細菌が重要な役割を果たしていますが、抗生物質のために腸内細菌バランスが崩れるとビタミンB2の吸収障害が起こり、口内炎が起こりやすくなります。抗生物質の内服のあとには乳酸菌やビフィズス菌の内服が勧められます。
痛み止めの薬(消炎鎮痛・解熱剤・抗炎症剤)によって胃粘膜傷害(胃潰瘍など)が引き起こされることはよく知られていました。胃の粘膜では、プロスタグランディン(PG-I2)という胃の粘膜を保護する物質が作られています。
一方、痛みのある場所では、 別の種類のプロスタグランディン(PG-E2等)が炎症の原因となっています。鎮痛剤は、この痛みの原因物質であるPGの生成を抑える働きにより、炎症(痛み、腫れ、熱)を軽くするわけですが、胃を守る物質も同時に減らしてしまうために胃粘膜障害が起こってしまうのです。
最近では、胃腸傷害の合併を減らす努力、工夫もいろいろとされるようになりました。プロドラッグといって血液中に吸収されてから有効な成分に変化するような薬が開発されてきました。炎症部位で悪さをしているPGの方をより選択的に抑える薬剤(COX2阻害剤など)の開発もされています。
また、薬を使う量を細かく調節したり、胃の粘膜を保護する薬をいっしょに投与するなど、薬の使い方にも工夫がされるようになりました。
鎮痛剤による胃潰瘍の特徴は、多発性、難治性で自覚症状に乏しいとされています。頭痛薬やかぜ薬を常用したり、連用するのは危険です。やむを得ず鎮痛剤を連用している人は、胃薬を併用したり、定期的に内視鏡検査を受け、胃腸障害に注意しましょう。
Q28:解熱剤と副作用について?
A28:過去解熱剤はその副作用のため使用されなくなったものも多くありました。
アミノピリンはかっては世界中で広く使用された解熱剤でしたが、血液に無顆粒症という重篤な副作用のために使用されなくなりました。
アスピリンは現在なお世界で広く使われていますが、少しずつ副作用が知られるようになってきました。そのいくつかは気管支喘息の誘発(アスピリン喘息といわれます)、胃腸障害と消化管出血、急性腎不全、ライ症候群、などです。
最近では解熱・鎮痛薬とインフルエンザ脳症との関係が明らかになってきました。
この中で解熱剤の副作用が急速に注目を浴びるようになったのは、アスピリンと小児のライ症候群との関係が疑われるようになってからです。1981年アメリカではすでにインフルエンザや水ぼうそう(水痘)ではアスピリンの使用が勧告され、1986年小児へのアスピリンの使用が禁止されました。
ライ症候群は、ウィルスなどの上気道感染のあとに急速に脳症(おう吐、意識障害、けいれんなど)、肝機能障害などの多臓器障害、血液検査異常がみられます。2~10歳代の小児の10大死因の一つといわれており、死亡しなくてもあとに著明な脳障害を残すことがあります。
ライ症候群は全身の細胞内のミトコンドリアの障害によって起こると考えられています。小児にウィルス感染などの先行疾患があり、それにミトコンドリアの機能を抑制する因子が加わることによって発生するのではないかと考えられるに至り、その因子の一つとしてアスピリンが疑われるようになりました。
現在先進国では小児にはアスピリンはほとんど使用されなくなりました(ただし川崎病では血栓症の予防目的で使われます)。また、大人でしばしば使用される非ステロイド系抗消炎薬を小児に解熱剤として使用することもほとんどありません。
アスピリンと非ステロイド系抗消炎薬が小児に使用できないのであれば、小児へ使用できる解熱剤は現在のところアセトアミノフェンしか見あたらず、世界的に使用されるようになってきました。
解熱剤として処方される場合に、頓用として与える方法と一日に定期的に与えられる方法が行われてきました。有効な血中濃度が得られないような中途半端な量や熱がないときに予防的に使用することは合理的ではないといえるでしょう。
副作用の発生の可能性もあることを考えると、解熱剤の使用は発熱時のみに使用するのが基本的ですが、必要な場合には発熱前の使用も認められるでしょう。解熱剤の長期連用は避けるべきです。
Q29:抗生物質やかぜ薬によるアレルギーについて教えてください。
薬のアレルギー反応はアナフィラキシー反応といわれる即座型のものです。薬を服用または注射後して数分後から30分後くらいで、じんましん様発疹、顔面蒼白・冷汗、血圧低下、呼吸困難、意識障害などが急速に起こってきます。
このようなショック症状や前駆症状が認められたときには、できるだけ早く救命処置をしないとショック死に至る怖いものです。
このような激しいアレルギー反応はアナフィラキシーショックといわれますが、ペニシリンアレルギーやピリンアレルギーもこれに含まれます。激しいアレルギー反応は一般に注射をしたときに現れやすいものですが、内服でも起こることがあります。投与量とはあまり関係なく、アレルギーテストに使用したごく少量のテスト液でも起こることがあり、注意が必要です。
ペニシリン系の抗生物質は、このようなアレルギー反応と耐性菌の出現から使用頻度は減少してきました。ここに一つ問題点があります。本人がペニシリンアレルギーやピリンアレルギーと思っていても、実際には違う場合が意外と多い点です。
しかしアレルギーの家族歴があるときや本人の申告があるときには、ペニシリン系抗生物質やピリン系薬物を使う必要性は少ないでしょう。
よく使用されるセフェム系抗生物質はペニシリンアレルギーのような激しいものは比較的少なく使いやすいといえますが、アナフィラキシーショックがないわけではありません。
医師の側としては問診を十分に行い、注射を行うときには慎重にテストを行うこと、万一、アレルギーを起こした場合を想定して、救急処置をすぐに行えるように常から用意をしておくべきでしょう。
アナフィラキシーショックのような激しいアレルギー反応でなくても、薬による発疹(薬疹)はしばしばみられます。
ピリンアレルギーによるピリン疹は有名ですが、このような薬による発疹がみられたときには、薬の服用を中止して医師の診断を受けることが必要です。くすりを飲み続けると次のような重篤なアレルギー反応を起こすことがあり、注意が必要です。
スティーブンス-ジョンソン症候群は皮膚と粘膜に滲出性紅斑とびらんを生じて全身に広がり、消化器症状、腎障害、意識障害などを合併して、緊急スティーブンス-ジョンソンを要する重症な薬物アレルギーです。
中毒性表皮壊死型薬疹(TEN)も重篤で、皮膚の疼痛と紅斑、水ほう、表皮はくり、びらんを生じ、多臓器不全に陥る危険性があります。
皮膚の発疹以外にも血液障害が起こることがあります。血小板減少症や顆粒球減少症(白血球減少)、肝機能障害が起こることもあります。さまざまな薬でこのような血液の異常がみられることがありますが、ふつうはゆっくりと進行することが多く、定期的な血液検査で気づくことが多く、薬を中止したり変更することで改善します。
しかしこのような血液の異常が急速に起こると、出血や感染を起こしやすくなりきわめて危険です。さらに急性腎不全の約3割は薬物アレルギーが原因であるといわれています。この中でかぜ薬により、急激な腎機能障害を起こすこともまれならず経験されます。
薬を飲んで何か体調や皮膚の変化を生じたときには、薬の内服を止めて医師の診察を受ける慎重さが必要と思われます。
Q30:アスピリンとピリンの違いについて教えてください。
A30:アスピリンは非ピリンとも呼ばれサリチル酸系に含まれる薬剤で、ピリン系(ピラゾロン系薬物に含まれる)の薬剤とはまったく違うものです。
ピリンという名がついているために、アスピリンとピリンは同じ種類の薬と混同されることがありますがそうではありません。
さてピリン系の解熱・鎮痛薬は「ピリン疹」というアレルギーの発疹を生じることがあります。そのような体質を持っている人にピリンを投与すると、激しいアレルギー反応を起こすことがありたいへん危険です。
その昔、かぜなどの発熱時にピリン系の薬剤を点滴や静脈注射で投与したことがありました。発熱はすぐに治まったものの、重篤なアレルギー反応のため死亡者が相次いだために使用は禁止されました。
ピリン系の薬を使う機会はたいへん少なくなってきましたが、現在医師により使用されるピリン系の薬の代表は次のようなものです。解熱目的でスルピリン(商品名:メチロン)、片頭痛の治療目的で使用されるアンチピリン(商品名:ミグレニン、クリアミンA)、頭痛薬のセデスG、サリドン(現在メーカーからの供給は中止されています;市販薬のセデスには非ピリン系のものがあります) などです。
アスピリンは現在もなお非常に多く使われています。小児へのアスピリンの使用は特別な場合を除いて(川崎病にはアスピリンが使用されます)、解熱・鎮痛の目的では使われなくなりました。
その理由は、インフルエンザや水ぼうそうでアスピリンを使用するとライ症候群という脳症を起こす可能性が指摘されたこと、また小児では重篤なアレルギー反応(スティーブンス-ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死型薬疹)を起こす場合があることなどです。
大人では解熱・鎮痛の目的でしばしば使用されます(商品名:バッファリン)が、むしろ少量のアスピリンを脳梗塞や心筋梗塞・狭心症の患者に血栓予防目的で投与することがしばしば行われます(商品名:バッファリン81、バイアスピリン)。
なお市販されている小児用のバッファリンはアスピリン製剤ではなく、アセトアミノフェンという製剤で、医師により処方される解熱剤(商品名:カロナール、アルピニー座薬)と同じものです。
アスピリンだけに限らず、解熱・鎮痛薬一般の副作用として、薬疹のような比較的軽いものから、胃腸障害・胃潰瘍、血小板減少症、顆粒球減少症(白血球減少症)、腎機能障害、肝機能障害などが起こることがあります。
Q31:授乳中ですがかぜ薬は飲んでも大丈夫ですか?
A31:産婦人科医の意見を聞きますと、妊娠七ヶ月以降は胎児のからだの発育はほぼ完成しているためにかぜ薬はふつうに飲むことができる と言われることがあります。
このように出産後は授乳中であっても、医師によって処方される一般的なかぜ薬は飲んでも乳児に影響があるとは言えないでしょう。
それでも薬は心配 と言われる方も多いと思われます。このような場合には、かかりつけの医師と相談の上、乳児でも内服できる抗生物質や解熱剤と同じ内容の薬を選んでもらうとよいでしょう。
かぜ薬として使用される大人の薬の中で、粉薬(細粒やドライシロップ)やシロップとして乳幼児でも内服できるものが多くあります。しかし今までにも述べてきたように、大人で使用される一部の解熱剤、消炎・鎮痛薬では、小児では使われないように指示されているものがあります。このような薬は授乳中は念のために避けておく方がよいと思われます。
※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。
※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。