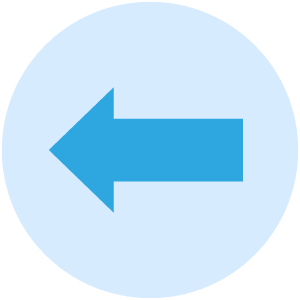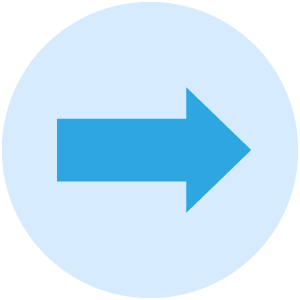皆様からよく聞かれる質問や疑問にについて Q and A 形式にまとめてみました。このページでは、「小児用肺炎球菌ワクチン」について解説しています。
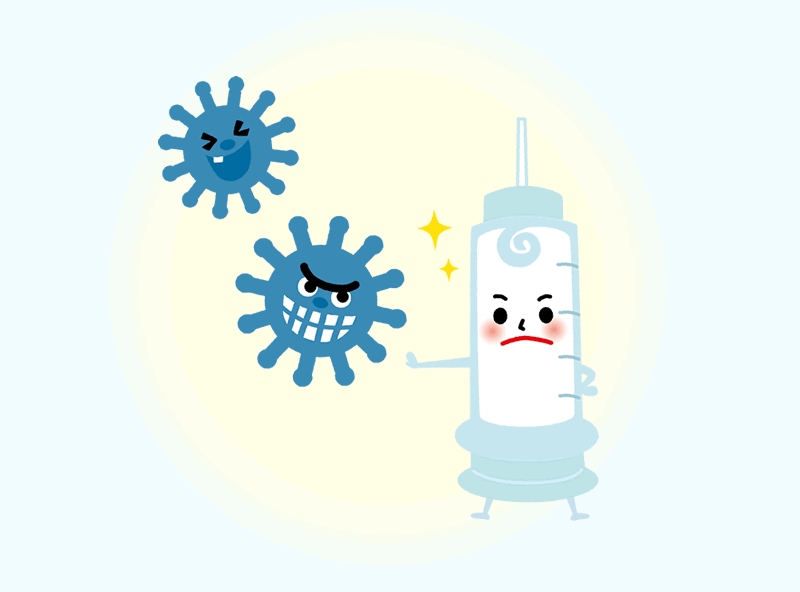
※このQ&Aは平成24年時点の情報を元に作成しています。最新の情報は予防接種情報(厚生労働省)をご覧ください。
・・・
Q1:早期産児や低出生体重児に接種する際に注意することはありますか?
A1:米国予防接種諮問委員会によれば、早期産児(妊娠期間37週未満)、低出生体重児に対しても、他の定期的な予防接種と同時に、推奨される実年齢で小児用肺炎球菌ワクチンを接種すべきである、とされています。
米国で実施された大規模無作為化2重盲検試験のサブ解析によると、小児用肺炎球菌ワクチン接種の有効性、幾何平均抗体価、全身性の副反応について、早期産児では正期産児に比較しておう吐が有意に多かったことを除いて、低出生体重児および早期産児と標準出生体重児および正期産児の間で有意な差はみられませんでした。
Q2:予防接種のスケジュールについて教えてください。
A2:2ヶ月齢以上9歳以下が対象となっており、標準として2ヶ月齢以上7ヶ月齢未満で接種を開始することとされています。
接種回数は初回(基礎)免疫が27日以上の間隔をあけて3回、追加免疫を3回目接種から60日以上の間隔をあけて1回で計4回となっています。
ただし、3回目接種については、12ヶ月齢未満までに完了し、追加免疫は標準として12~15ヶ月齢の間に行うこととされています。また、標準的な時期に接種を開始できなかった接種もれ者に対しては、7ヶ月齢以上12ヶ月齢未満の者では計2回、追加免疫が1回の計3回、12ヶ月齢以上24ヶ月齢未満の者は計2回、24ヶ月齢以上では1回のみとなっています。
以下の(1)が標準的な接種スケジュールですが、接種もれ者に対しては、(2)、(3)、(4)のように接種間隔および回数による接種をすることができます。
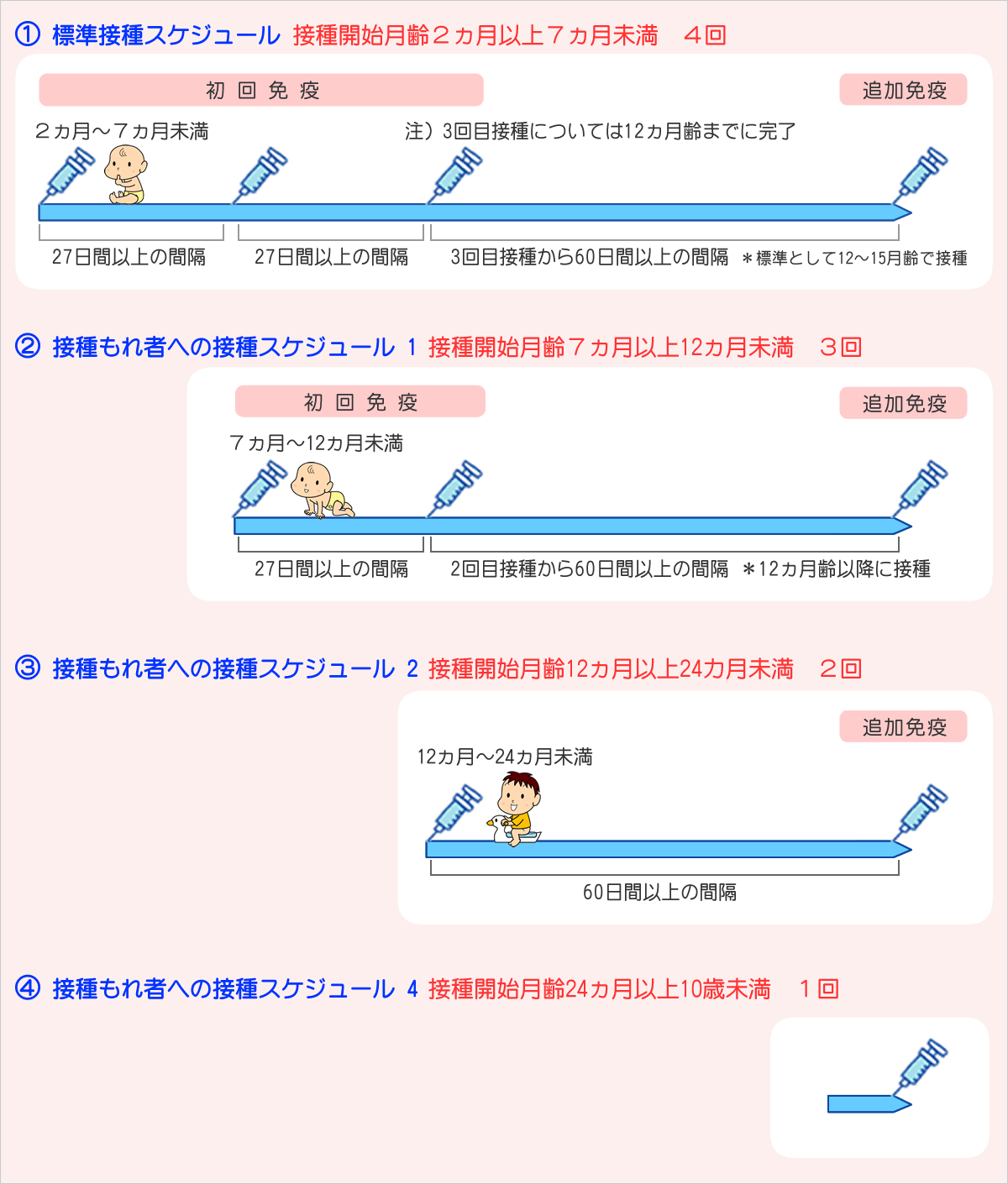
Q3:おもな副反応はどんなものがありますか?
A3:接種部位の局所反応として腫脹、紅斑、硬結などが認められますが、おおむね軽度で自然に回復します。
そのほか、全身的な副反応として、発熱、易刺激性、傾眠状態なども認められますが、米国の市販後有害事象調査では、有害事象の頻度は他のワクチンと同程度と報告されています。
副反応が認められた頻度は国内臨床試験の結果では、1回目接種で162/181例(89.5%)、2回目接種で154/177例(87.0%)、3回目接種で151/174例(86.8%)、4回目接種で144/169例(85.2%)となっています。
Q4:ワクチン接種を完了した場合、どの程度の期間、予防効果が持続しますか?
A4:小児用肺炎球菌ワクチン接種後の正確な予防効果の持続期間は、現時点では明らかではありません。
しかし、WHOが平成19年(2007年)に加盟各国に発表した予防接種に関する勧告の中で、ワクチン血清型による肺炎球菌感染症の発症予防効果は、幼児期のワクチン初回接種後少なくとも2~3年は持続することが記載されています。
さらに小児用肺炎球菌ワクチンの免疫原性データからは、他の結合型ワクチンと同様に、相当長期間にわたり予防効果が持続しうると考えられます。
Q5:わが国の小児用肺炎球菌ワクチンは小児用7価肺炎球菌結合型ワクチンと呼ばれますが、7価とはどういう意味ですか?
A5:肺炎球菌は菌体を覆うきょう膜の免疫原性(血清型)により約90種類に分類され、およそ1/4がヒトに病原性を持つとされています。
中でもとくに2歳未満の侵襲性肺炎球菌感染症の原因菌として頻度の高い7種の血清型に対する抗体誘導を目的に開発されたのが、7価肺炎球菌結合型ワクチンです。
調査結果によれば、ワクチンに含まれる7種の血清型(4、6B、9V、14、18C、19F、23F)に起因する小児侵襲性肺炎球菌性感染症は全体の77.8%になっていますが、血清型6Bと交差反応する6Aを含めたカバー率は83.1%となります。
欧州では肺炎と中耳炎、米国では中耳炎の予防も適応症になっていますが、本邦で薬事法上承認された効能・効果は、その治験の内容から「ワクチンに含まれる血清型に起因する侵襲性肺炎球菌感染症の予防」となっており、小児侵襲性肺炎球菌性感染症以外の肺炎および中耳炎は目下のところ適応症には含まれていません。
*小児侵襲性肺炎球菌性感染症についてはA6をご覧下さい。
Q6:小児の肺炎球菌ワクチンはどうして必要なのですか?
A6:肺炎球菌は、乳幼児の鼻咽頭に高率に定着する常在菌で、飛沫感染により伝播する小児の細菌感染症の主要な原因菌です。
保菌者のすべてが発症するわけではなく、抵抗力の低下や、粘液バリアの損傷などにより、宿主(ヒト)と菌の間のバランスが崩れて菌が体内に侵入すると発症に至ります。
疾患としては、髄膜炎、敗血症・菌血症、肺炎、中耳炎など多岐にわたりますが、とくに本来無菌であるべき部位(血液、髄液など)から菌が検出される病態である小児侵襲性肺炎球菌性感染症と称される髄膜炎、敗血症・菌血症、血液培養陽性の肺炎などがとくに問題視されます。
日本の小児において、次に挙げる各疾患で肺炎球菌が原因となる割合は、中耳炎31.7%、菌血症72%、細菌性髄膜炎19.5%という報告があります。
また、5歳未満人口10万人あたりの小児侵襲性肺炎球菌性感染症の罹患率は、厚生労働科学研究の平成20年3月の報告によれば、敗血症・菌血症9.8人、髄膜炎2.9人とされています。
小児侵襲性肺炎球菌性感染症は2歳未満の乳幼児でリスクが高く、ときに致死的であり、救命しても後遺症を残す可能性があるため、接種が可能になる2ヶ月齢以上の乳児では積極的にワクチンによる予防を高じることが重要になります。
Q7:小児用7価肺炎球菌ワクチンは海外ではどの程度普及していますか?
A7:小児用7価肺炎球菌ワクチンは平成12(2000)年の米国による発売以来、海外では10年間に多くの国で使われ、平成21(2009)年末現在、全世界で累計2億3500万回の接種が実施されています。
WHOは平成19(2007)年に「小児用肺炎球菌ワクチンを優先的に定期接種に取り入れるべきである」という勧告を加盟各国に対して発表しています。
平成22(2010)年2月現在101各国で承認され、98ヶ国で発売、45ヶ国で国が費用を負担して接種を推進する定期接種が実施されています。
Q8:同時接種など、小児用肺炎球菌ワクチン接種の際の注意について教えてください。
A8:接種に際しては医師による問診や診察、検温などを受けてから行うこと、同時接種について、現在の治験からは安全性について問題はないと考えられていますが、それぞれのワクチンを一つずつ単独で接種することもできること、基礎疾患を持っているお子さんは、一般に健康な乳幼児よりも感染症にかかると重症化のリスクが高く、重い感染症を早期に防ぐことも重要ですが、ワクチンによる副反応についてもより注意が必要であるとされました。
とくに重い基礎疾患のあるお子さんへの予防接種は、日頃から基礎疾患の状態をよく知っている主治医や、主治医と連携し予防接種の経験のある医師などが、子どもの体調をよく確認して、接種を受けるのに適した時期を判断し、慎重に接種を行うこととされました。
一時的な見合わせにより、接種の予定日を過ぎてしまった場合も、接種後の免疫効果には問題がないとされていることから、間隔が多少ずれたとしても、なるべく早く接種を受けることが望まれます。
《参考文献》
2011(平成23年)予防接種に関するQ&A集(岡部 信彦、多屋 馨子ら):一般社団法人日本ワクチン産業協会 から転記(一部変更)
※このサイトは、地域医療に携わる町医者としての健康に関する情報の発信をおもな目的としています。
※写真の利用についてのお問い合わせは こちら をご覧ください。